2024.06.07
テクノロジー
2024.05.24
テクノロジー

DX化というものが声高に叫ばれるようになった昨今。歯科業界も例外ではなく、様々な場面でDX化が進んでいく中で、データの取り扱い方と管理、デジタル化に伴うデータ管理の複雑化、異なるメーカーのデバイスやシステムを統合することの困難さなど、今まで考えることのなかった課題が顕在化してきています。
そんな中で歯科医院経営を健全に、かつ効率的に行っていく上でなくてはならないDXについて、どう考え、どう向き合っていくべきなのでしょうか。
本記事では、歯科医院におけるデジタル化とDX化の現状と課題について、日本臨床歯科CAD/CAM学会 北海道支部長でもある北海道石狩市高松歯科医院の高松雄一郎院長にお話を伺いました。
→前編
– 患者さん自身で自分の診療・治療情報を持ち、それを共有できる世界観。まさにPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)が実現する世界なのかなと思います。
高松:そうなってくれたらありがたいですよね。ただ多様なデータを一箇所に保存するということはきっと難しいのではないかなと思っています。現実的にはactionGATEのような形がPHRに近いのかなと考えていて、様々なメーカーのツールで保存され管理されているデータを一つのソフトウェアで見に行くみたいな感じのシステムですね。
– となると、PHRへの最初のステップとしては、今先生がおっしゃったactionGATEとメディットリンク(歯科医院と技工所間のコミュニケーションを効率的に行えるように支援するツール)組み合わせなのかなと思います。actionGATEで患者さんごとに管理されているデータをピックアップするように患者さん自身で見ることができるようになると近いことができるのかなと思います。
高松:そうですね。そうするとかなり近いものになりそうですよね。それだと今のプラネットさんのシステムで、診察券のアプリがあるんですが、そのアプリで今まで紙で渡していたような検査値のデータを、これ閲覧していいですよという許可を患者さんに与えられるんです。そうすると患者さんは、紙なしでそれを見ることができるし、スマホに送って、端末で確認してもらえます。見積もりもそれで確認できたりしますね。

– レントゲンの画像や口腔内写真もできるんですか。
高松:できると思います。レントゲンはプラネットで管理してないので私の医院ではできないんですけど、口腔内写真はそういう形でやっていますね。口腔内写真は視覚的にわかりやすいので患者さんにとっても、今日良くなったところや、ホワイトニングで白くなってきていることなどが明確にわかります。それは「また通わなきゃ」とか、逆に「ちょっと悪くなってるから通わなきゃ」のような心理的なモチベーションを作ってくれると思いますね。
患者さんも、紙で渡されるよりタブレットで見られた方が便利でしょうし、方向性としても良い方向性なんじゃないかなと思います。
– データの統合を望む声は多いとは思いますが、メーカー間での思惑など解決するための壁は多くありそうですね。
高松:そうですね。でもそういうことをやる会社さんが少しずつ出てきてると思うんですよ。例えばデルタンオーダー(技工依頼を一元管理できるシステム)です。
データの統合というのは技工所サイドからしてみたらすごく大きなことだと思うんです。それこそ様々なメーカーの様々な種類のデータがわんさか来て、プラットフォームもバラバラで技工に関するデータがくるわけですよね。詳しくわからないですが、それを一元管理できるならば、これだけ仕事が来てるんだっていうことが一目でわかる。それって受ける側としたら、大きい会社になればなるほどありがたいんじゃないかなと思うわけですよ。
– CAD/CAM、技工所関連はそういった流れは強いのかもしれませんね。確かにデータを統合できるということは、ミスを防げるっていうのもあるんですね。
高松:そうですね。デジタルのいいところってコピペをするとか、データ同士を紐付けるとか、何かザクッといけるみたいなところがメリットなのに繋がらないとそれができないわけです。つまりフルスペックで活用できてないっていうことになるわけですが、多分そこが今後のデジタル化、DX化した後の伸びしろなんだろうなというイメージでいますね。
– そういう感覚を皆さんの中で持っていたら必ず将来、その需要を満たすものが出てきますよね。
高松:本当にそうだと思いますね。実際にできつつあるんだと思いますが、バックオフィス系でいうと、アポ帳とかレセコンとか、あと決済もそうですよね。
そういえば、北海道の材料屋さんで、在庫を把握するアプリを作っているところがあるんですが、これがすごいんですよ。まだ開発段階なんですが、院内の在庫事情が全部ばれてるんですよね(笑)
ある在庫がなくなってきて、注文する前にちょっと別のところの方が安いかもしれないから様子見てから注文しようかなと思っても「もう在庫ないんじゃないですか?」って通知が来るように把握されているわけです。高精度のアプリを開発してるんだろうなと思うんですけど、そういったものも出てきてます。面白いですよね。
発注とかも自動化がほぼできるという話ですが、業者さんにとっても営業さんが回らなくていいとなりますし便利ですよね。
– 需要を満たす高性能なシステムやサービスが数多く出てきている時代だからこそ、データ連携ができるかどうかが選ばれるポイントになりそうです。

高松:多分これからはそうしてほしいって思う人が増えると思うんですよ。5年前だったらとりあえずDXと言われていました。そのときはデジタルデンティストとか言って、デジタル化をしていくんだっていう流れでした。その筆頭が口腔内スキャナーだったというわけですけど、今はもうデジタルデンティストって言ってる人がほぼいなくなってしまいましたよね。もう何でもかんでもDXって言うじゃないすか。
ということは、それは当たり前になってきてると思うわけです。ですから次にDXと言われなくなる頃には、連携するものから選択するっていう考え方が先に来ること多くなるんじゃないかなと思うんですけどね。
– そんな遠くない未来なのかなっていう感じがします。
高松:そんな感じもしますよね。DXもコロナになってからですかね。歯科でも流れが来始めてからもう3年そこそこ。
あと2、3年後にはもうDXとも言われなくなりそうな雰囲気があるので、次は・・・何かメタバース的な何かなのかはわからないすけど(笑)
– 素朴な疑問なんですが高松先生はどこからDXに関する情報をキャッチアップされているんですか?
高松:学術大会などで展示されてるところとかが多いですね。イノベーティブな会社さんとかも時々展示されてるときもありますし、あんまり札幌だと味わえないようなものが、本州までくれば結構あるので(笑)
ただそういうところに歯科医師さんが行く場合、興味関心は治療のことだと思うんです。当然、そこに興味があるから歯科医師をやっていると思うんですが、とはいっても治療をちゃんとやるためには、バックオフィスの整備をきちっとやらないといけないと知ってほしいですね。歯科医院はその両輪で回ってるものですから。
そういう目線で学会などにいくと、イノベーティブな会社さんの展示などに目が行くようになりますし、そこから何か取り入れてみたいなという気持ちになると思うんです。そうなってくると今使ってるメーカーさんで「そういうものないんですか?」というような会話が生まれて、メーカーさんも「実はこういうのがあってね」という会話につながってきたりするものなんです。こっちから発信しないとメーカーさんとかディーラーさんは意外と教えてくれないことってあるんですよね。できるんだったら言ってよみたいな感じなんですけど、誰にでも必要な情報とは限らないからなんでしょうね。
– たくさんお話を伺いましたが、高松先生は開業時からここまでDXやデジタル化への意識は高かったんでしょうか?
高松:いやいや、全くそんなことはなかったんです。
– 先生の場合、CAD/CAMというかなりイノベーティブな製品を取り入れて、データの重要性などに気づかれたんでしょうか。
高松:そうかもしれませんね。データの統合というところだと、プラネットさんと関わっていた時があるんですが、プラネットさんは元々口腔内写真の管理や検査値などを患者さんに見える化してあげるような感じのメーカーさんだったんです。それが2014年ぐらいからレセコンをやりだしたり、アポイントソフトウェアもリリースしたんですよね。
そこで気づいたんですよね。データはまとまっていた方が楽だと。
アポ帳のシステムは、元々プラネットさんじゃないものを入れていました。すごく良くて安いシステムで、スタッフの中でもこれがいいって評判だったんです。でも、プラネットさんの連携できるシステムの方が最終的にはいいんですよ。
というのもアポ帳を見て、そこをタップすればレントゲンも見られる。タップすれば、口腔内写真も見られる。これがすごく楽だと気がついたんです。アポ帳システム開いて、口腔内写真のシステム開いて、レセプトのシステムも開いて、ということをやらなくていいわけですからね。
– なるほど、確かに高松先生に今お話いただいたのようなことは医院さんが目の前の患者さんに集中できる一つの鍵かなと思っていて、無駄な時間というと失礼ですが、統合したことによる手間、そして時間の削減は大きいと思います。その分だけ目の前の患者さんに集中できるということがあるべき姿なのかもしれませんね。
高松 雄一郎(タカマツ ユウイチロウ)
高松歯科医院 院長
北海道医療大学歯学部 卒業
北海道大学高齢者歯科学教室入局
北海道大学大学院歯学研究科入局
日本臨床歯科CADCAM学会 北海道支部長
ISCD国際セレックトレーナー
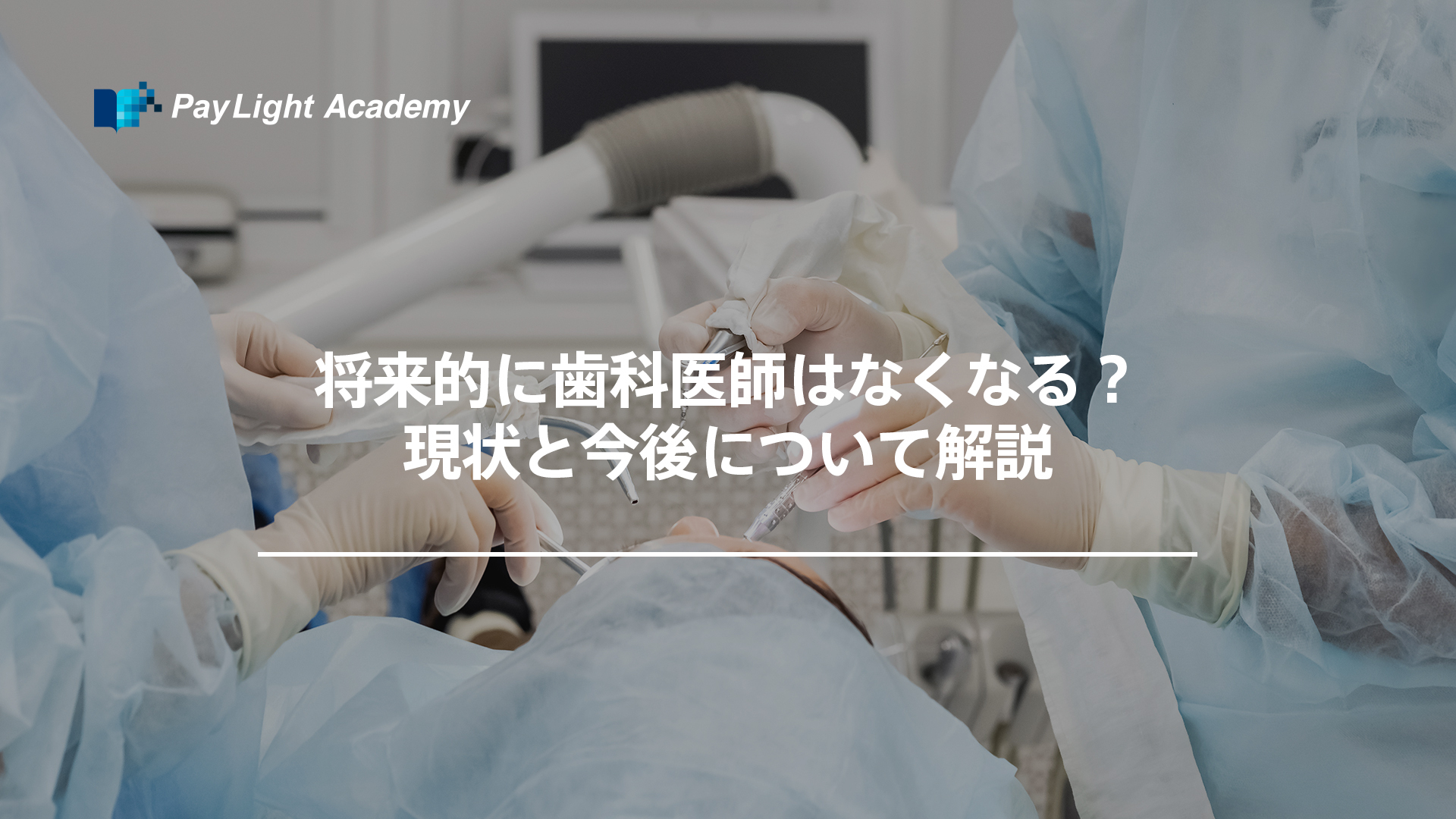
2024.04.02
経営
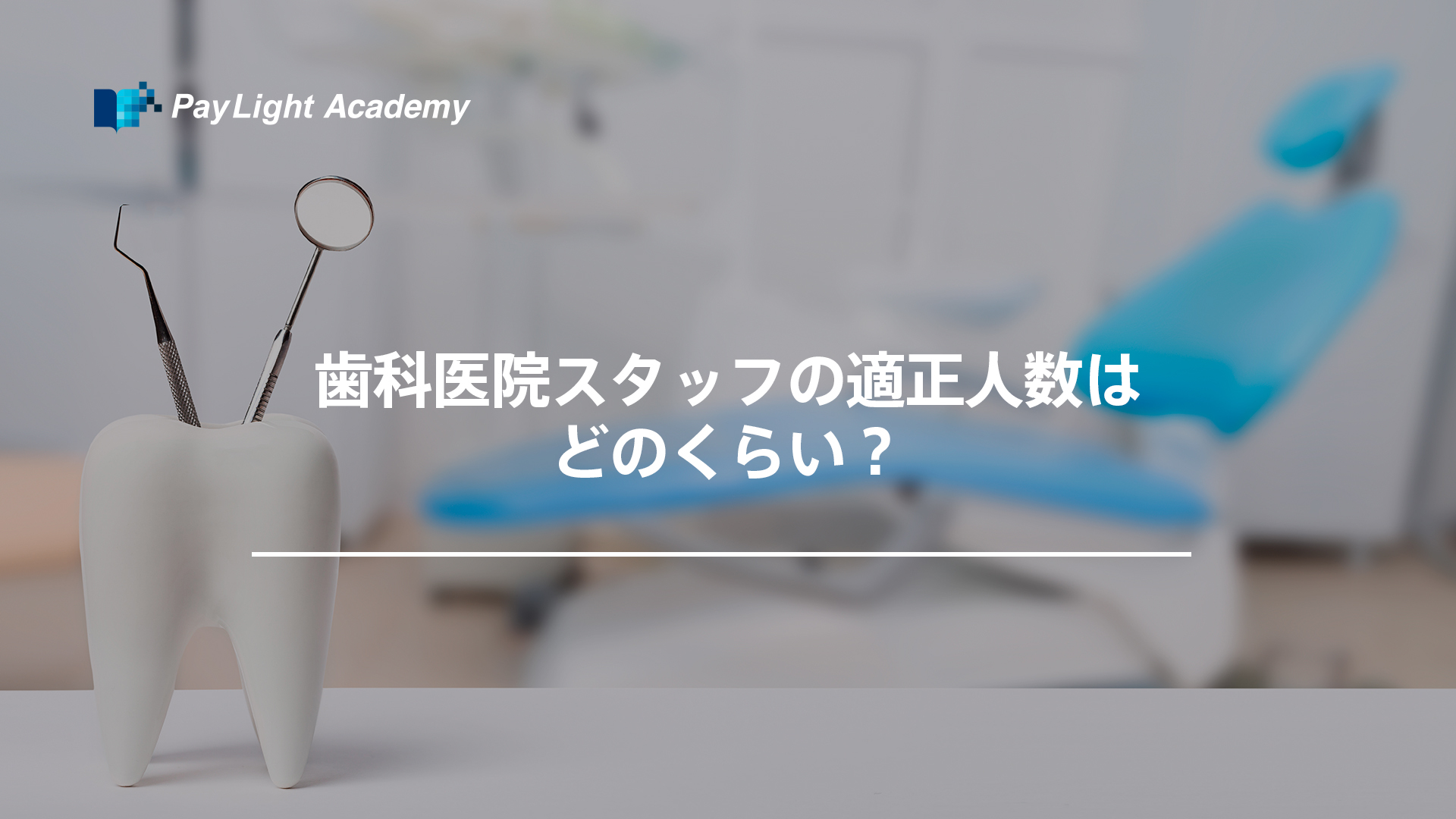
2024.03.11
経営

2023.12.13
経営
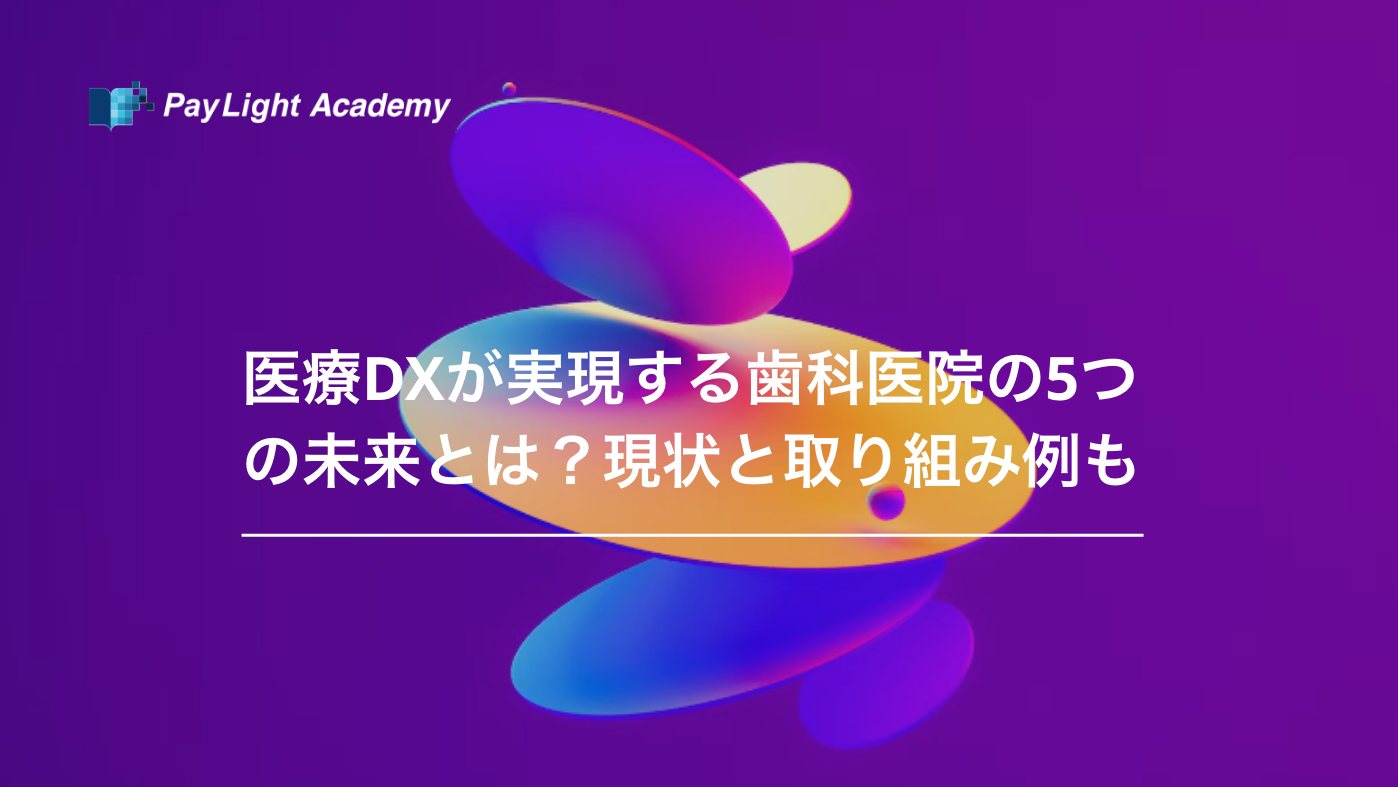
2023.12.13
テクノロジー

2024.05.10
テクノロジー
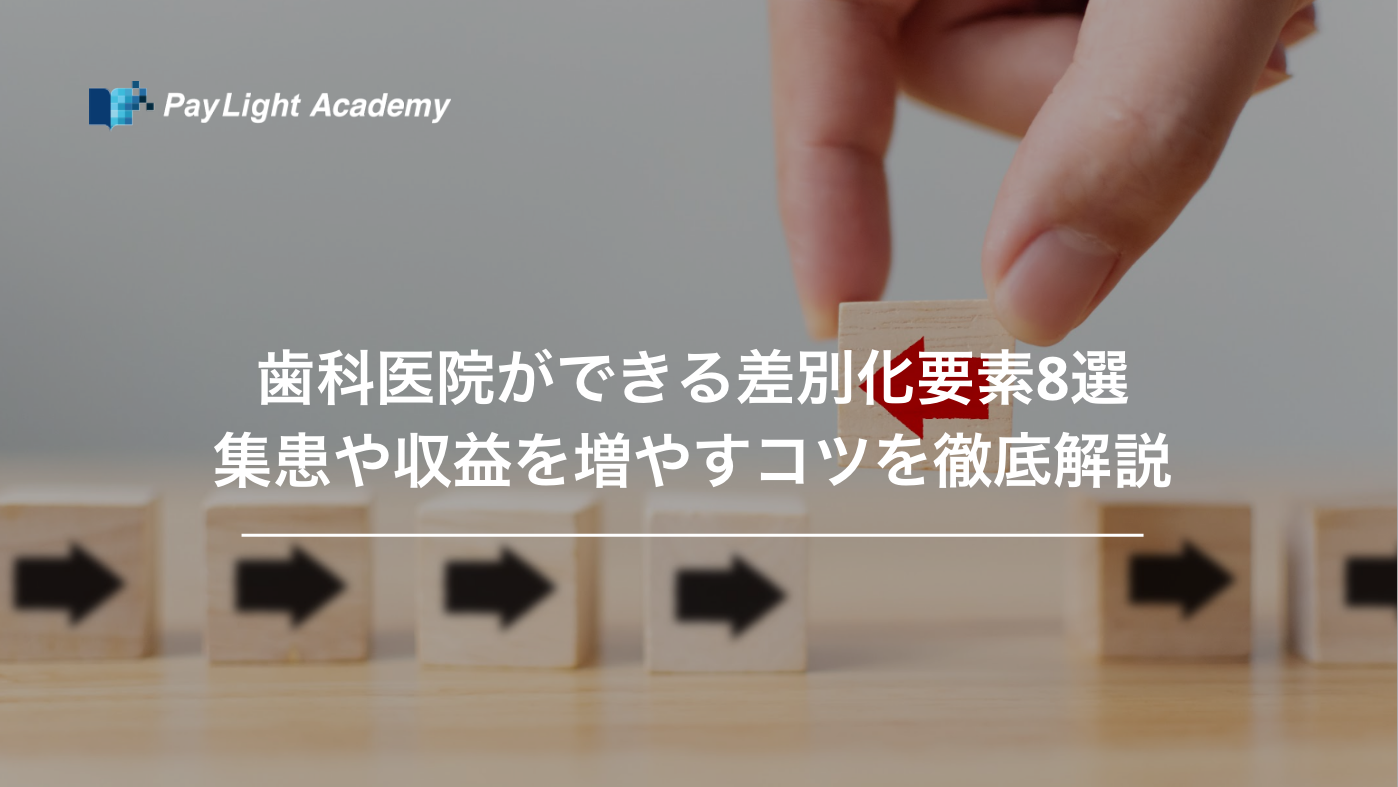
2023.12.13
経営
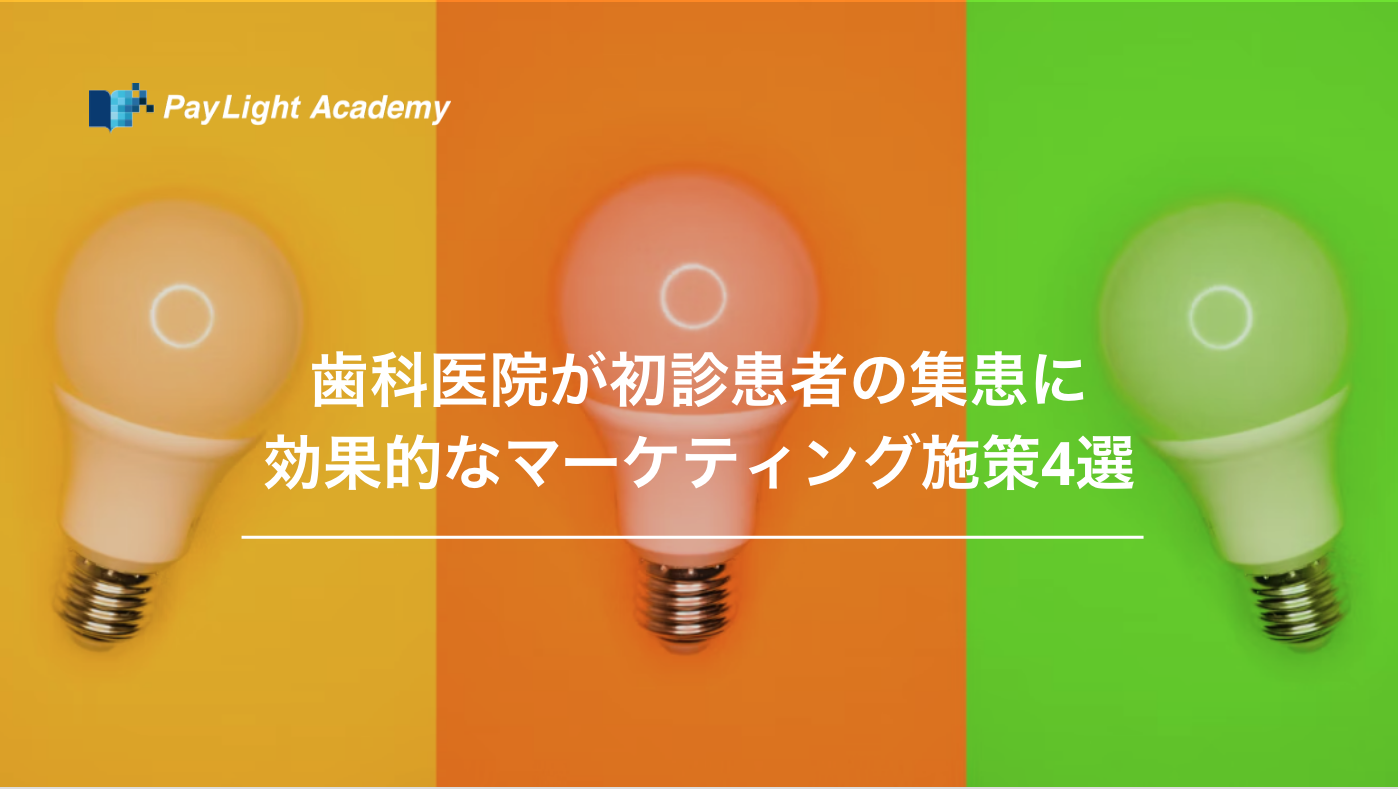
2023.12.13
経営

2024.05.24
テクノロジー