2024.04.26
経営
2024.04.02
経営
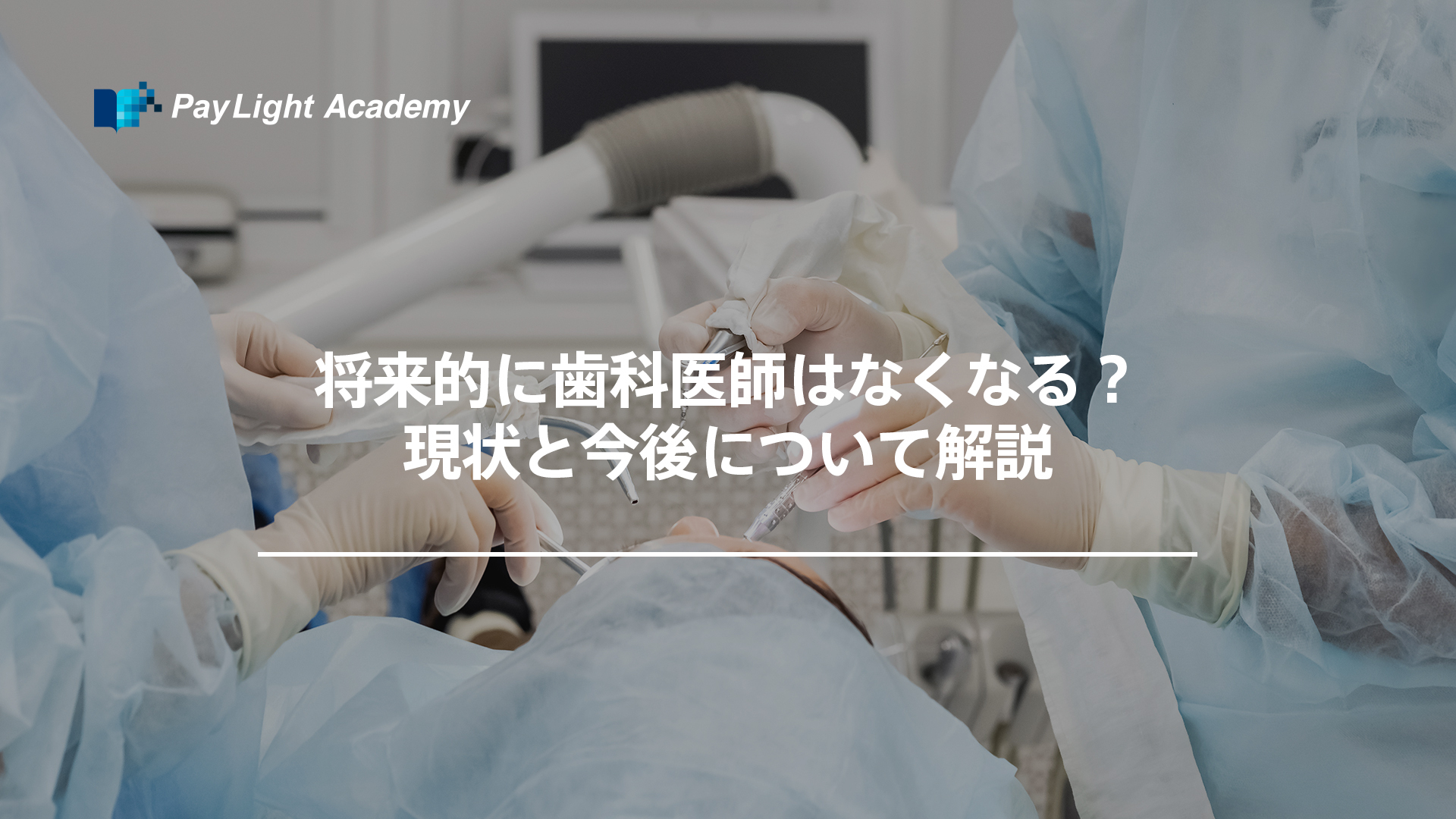
「歯科医師は将来なくなってしまうのか?」
「自分が歯科医師として今後生き残っていけるか不安」
歯科医師を目指している人はもちろん、現在歯科医師として働いている人も、上記のような悩みを抱えているのではないでしょうか。
毎年新たな歯科医師が誕生している一方で、日本の人口は減少し続けているので、歯科医師の供給が過剰になる可能性があります。しかし、口腔内の健康管理や治療などは欠かせないため、歯科医師の仕事がなくなるわけではありません。
この記事では、歯科医師の現状や将来起こるであろう需要の変化、今後の取り組みを紹介します。歯科医師の将来性が気になる人は、ぜひ最後までご覧ください。
結論を言うと、日本全体で見れば将来歯科医師が不足する可能性があります。実際、日本歯科大学協会常務理事の櫻井薫氏は「2025年から歯科医師数が減少に転じる」と発言しています。1
令和2年の人口当たりの歯科医師数は、経済協力開発機構(OECD)加盟38カ国中19位と過剰とはいえません。むしろ超高齢社会で歯科へのニーズはさらに高まると予測されています。2
また、歯科医師国家試験の合格者も減少しています。2023年の歯科医師国家試験の合格者数は2,006人でした。一方、20年前の2003年の合格者は2,932人であり、そこから合格者数は減少、近年は2,000人前後で推移しています。34
高齢の歯科医師がリタイアすることも想定すると、歯科医師が減少に転じる可能性は十分に考えられるでしょう。
今後20年間は過剰状況が続くとされながらも、歯科医師不足が懸念される理由は以下のようにいくつかあります。
順番に詳しく見ていきましょう。
歯科医師不足が懸念される理由のひとつに、歯科医師国家試験の合格者数が減少していることがあげられます。歯科医師の質向上を目的として、歯科医師の養成機関を削減する国の方針にともない、合格基準も見直されたためです。
一定の合格点に加え上位何名までが合格という相対評価を採用していることが、合格率低下の要因になっているでしょう。
2023年は受験者数3,669人に対し、合格者は2,006人(63.5%)でした。およそ20年前は合格者が3,000人前後だったことからも、歯科医師の供給が減っている事実が分かります。[注3参照]
歯科医師数の偏りは今後ますます広がる可能性があり、地域によっては歯科医師が不足すると考えられます。人口10万人に対する歯科医師数は、最多の東京都が約120人に対し最少の青森県が56.5人と2倍以上の差があります。
令和5年の厚生労働省調査では、簡単には歯科医療を受けられない地区が1,200地区以上あることも分かっています。全国総数にすると約18万人が、歯科医療を受けられない現状は深刻な問題といえるでしょう。5
歯科医師が集まる都市部では競争の激化が起きている一方、地方では歯科医師不足が進んでいる二面性があります。

歯科医師の約9割は、歯科医院で地域の口腔保健に貢献しています。
歯科医院を経営する代表者の年齢は約6割が60歳以上です。2023年時点で67,269ある歯科医院数は減少の一途をたどっており、歯科医師の高齢化が要因と推測されています。[注2参照]
令和2年の歯科医師の年齢は50~59歳が最も多く、60~69歳が後に続きます。50~69歳の歯科医師で全体の45%を占めており、社会全体の高齢化の例に漏れず歯科医師の高齢化も進んでいるのです。6
最も多い年齢層である50~60代の歯科医師が70~75歳で大量にリタイアすることを想定すると、数年後には歯科医師数が激減すると考えられるでしょう。[注2参照]
歯科医院の院長が引退した後に、後継者がいないことも深刻な問題です。自身がリタイアした後の後継者に関するアンケート調査では、歯科医院の9割で継承が決まっていないと回答しました。[注2参照]
事業承継は実子や親族・従業員・第三者などに自院を引き継いでもらうケースが一般的でしょう。ただし実子や親族・従業員に継承の意思や適性がないことも考えられます。
承継する人物がいなければ、院長の引退がすなわち歯科医院の閉院につながります。特に地方においては、歯科医院が一つ減ることの影響は大きいでしょう。
今後の日本の社会構造を想定した場合、口腔内の外来診療がメインである歯科医師の需要について以下のような変化が考えられます。
それぞれ詳しく説明します。
今後は通院が難しい高齢者に対する、訪問歯科の需要の拡大が見込まれています。歯科医院全体の患者数は2045年に約10%減少する一方で、65歳以上の患者は増加する予測のため、高齢者向けの治療のニーズが高まるでしょう。7
高齢者の口腔ケアは口の中の衛生環境を整え、心臓病や糖尿病、認知症などさまざまな疾患の予防につながります。患者とその家族の介護負担の軽減のためにも、訪問歯科の需要は今後拡大する可能性が高いでしょう。
人生100年時代を見据えての予防・ホワイトニング・矯正の需要が急激に伸びています。8
従来の歯科医院の主な需要は虫歯治療でした。しかし、歯磨き習慣の浸透やフッ素入り歯磨き粉の普及などもあり、虫歯罹患率は減少傾向にあります。9
そのため、将来の歯科医師には単純な治療だけでなく、審美系の治療といった付加価値の高い治療も求められるでしょう。
今後は虫歯治療にとどまらず、顎関節症(がくかんせつしょう)などの難しい治療や再生医療など、より高い技術が求められていく見込みです。

将来も社会から求められる歯科医師になるためのポイントは、2つあります。
1つずつ詳しく解説します。
激変する歯科業界に対応するには、歯科医院独自の専門分野を確立することが重要です。ニーズの多様化は、裏を返せば特定分野の専門性が求められていることを意味します。
例えば、厚生労働省は専門医制度を認定しており、以下の分野で専門性が認められればそれを広告できるようになります。10
専門医の資格を取得し専門分野を磨くことは、強みになるでしょう。
歯科医師数が仮に減少していくとしても、自らの専門性をさらに高めていくことで過度な競争は避けられることが予想されます。
歯科医院の開業は、歯科医師の代表的なキャリアパスの一つです。歯科医師全体では56%、60代では81%が開業しています。11
歯科医院の開業には、以下のメリットがあります。
小児歯科や矯正歯科など、扱う分野も自身で決められるのもメリットの一つです。ただし開業をしたら歯科医師であると同時に経営者にもなるため、マネジメントやマーケティングのスキルの習得も重要になります。
歯科医師は国民一人ひとりの口腔の健康を維持していくために重要な存在です。自らの専門性を高め、自分にしかできない仕事に取り組みましょう。
近い将来、歯科医師数は過剰供給ではなく不足する可能性があります。歯科医師が不足する要素として上げられるのが、以下の4つです。
今後は訪問歯科や高技術治療などの需要の変化に対応すべく、開業を視野に入れながら専門分野を確立することが重要でしょう。
患者からの需要が変化し過剰供給という認識が改められようとしている歯科医師には、活躍の場が広がるチャンスかもしれません。
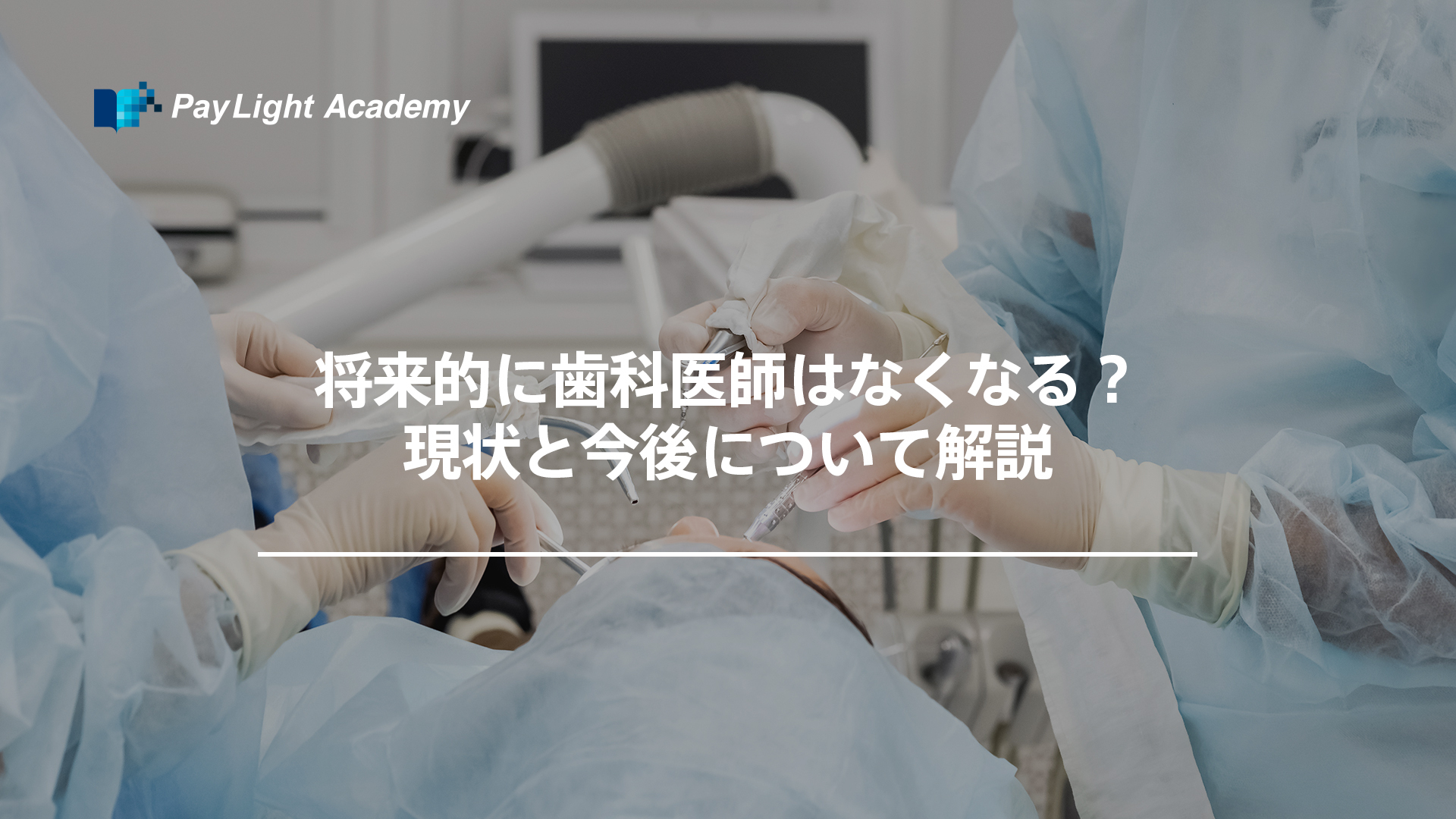
2024.04.02
経営
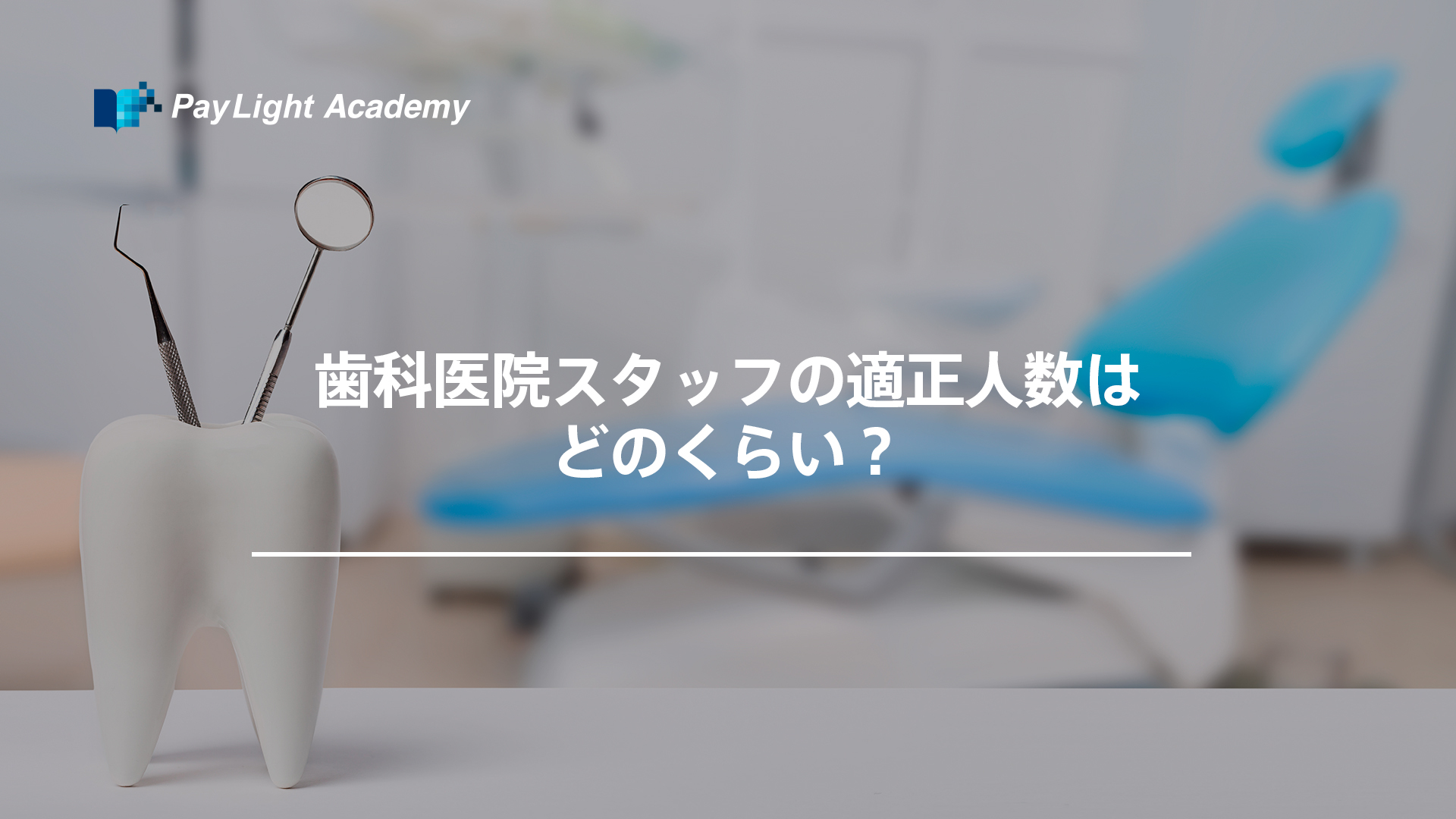
2024.03.11
経営

2023.12.13
経営
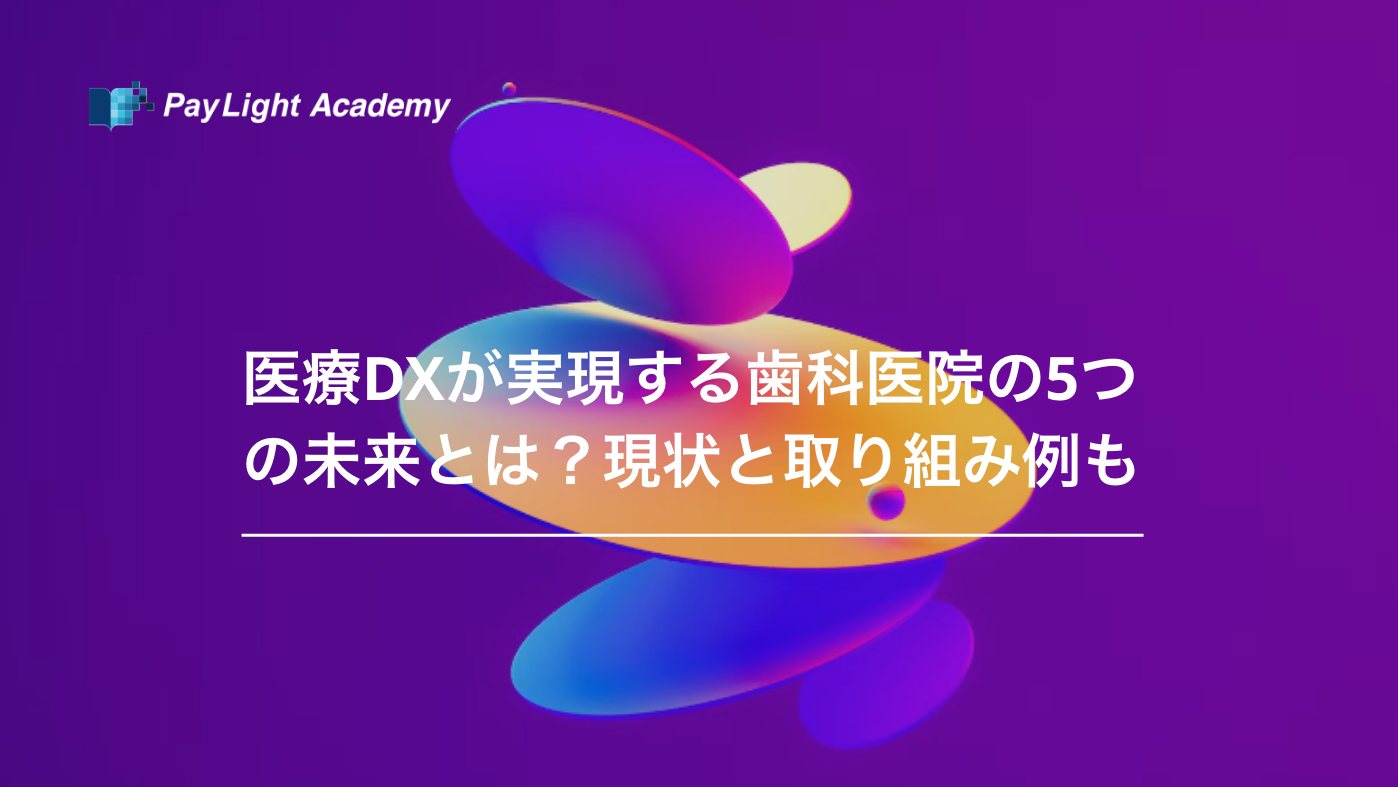
2023.12.13
テクノロジー

2024.05.10
テクノロジー
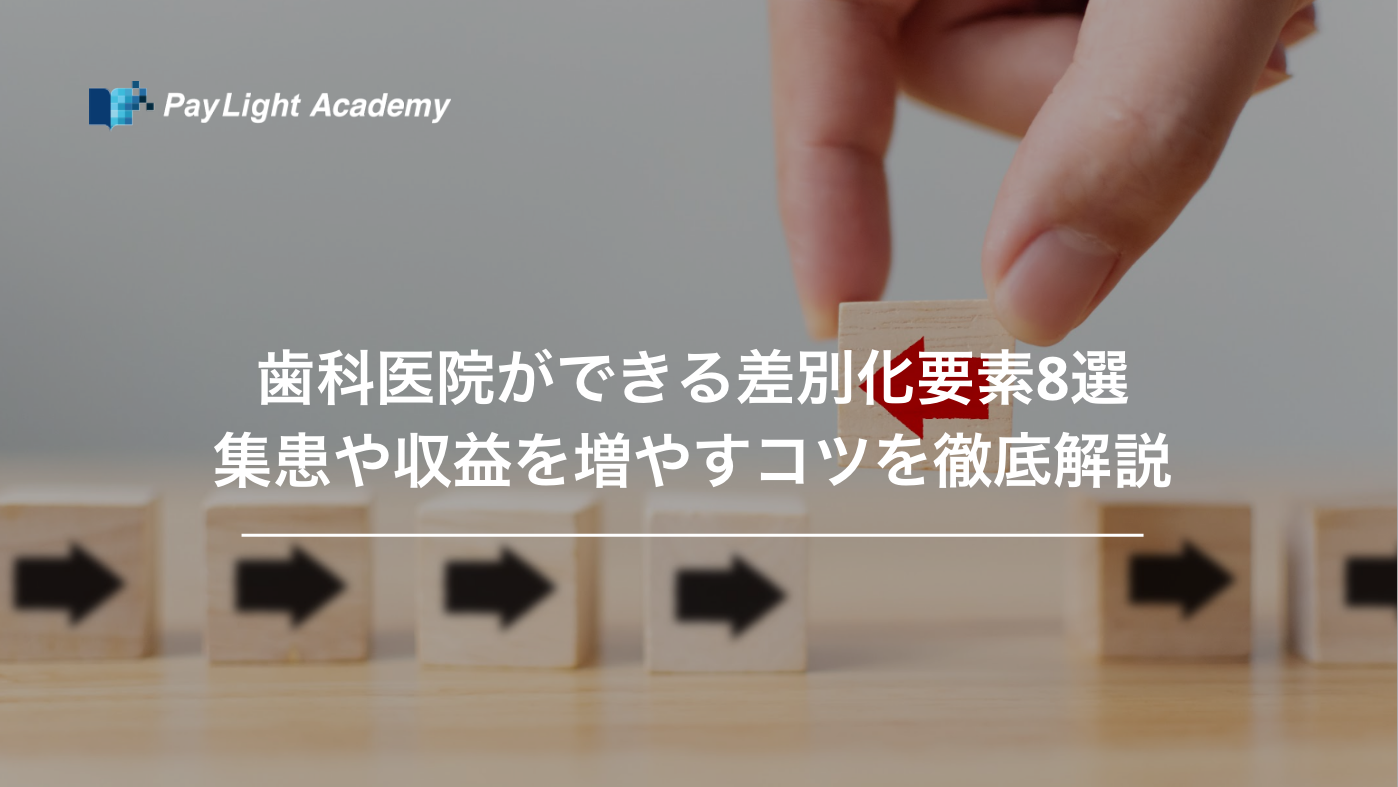
2023.12.13
経営
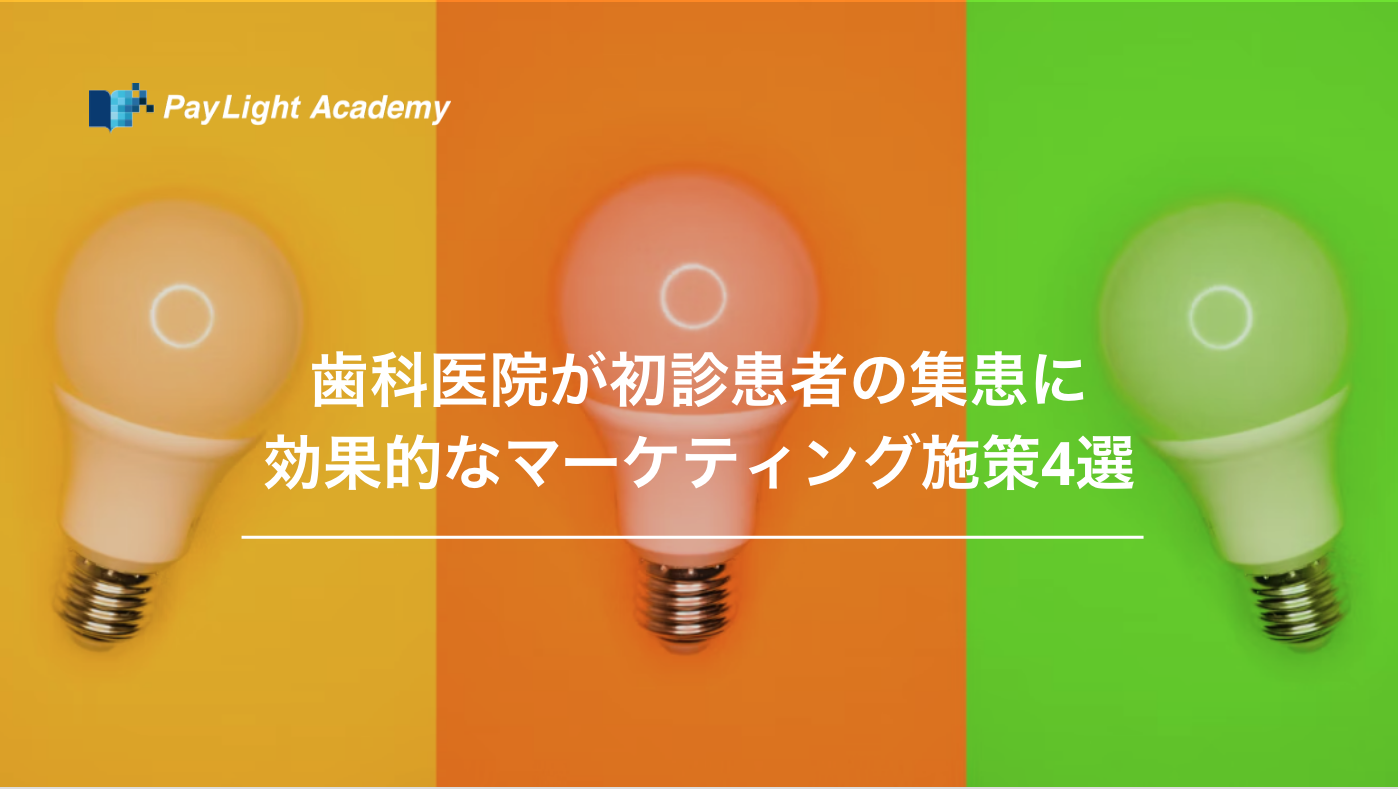
2023.12.13
経営

2024.05.24
テクノロジー