2024.06.07
テクノロジー
2024.02.09
テクノロジー

歯科医院を経営されている方ならば一度は頭を悩ませたことがあるであろう受付業務。単純に歯科医院の受付は煩雑、多忙を極めるだけでなく、人手が足りない、有能なスタッフが退職してしまい業務が回らなくなってしまったなど課題は多いものです。
「DX」「業務効率化」とは聞いたことはあるけれど、他の医院はどのように取り入れているのだろうか?何を基準にシステムを選んでいるの?スタッフの反発はないのだろうか?など気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、歯科医院の受付周りにおける業務効率化、現在の取り組み状況や課題、理想の受付のあり方などについて、新栄町歯科医院院長の佐久間利喜先生にお話を伺いました。機械化のメリットや効率化に向けた投資判断基準などについても話を伺っているので参考にしてみてください。
-便利な業務効率化ツールですが、無料で入れられるわけじゃないですよね。お金がもちろんかかってくるわけですが、佐久間先生は成果と費用の兼ね合いってどう考えていらっしゃいますか。
佐久間利喜(以下佐久間):僕がいろんな機械を入れるときに考えてることが、まず5年で回収できるかどうかです。5年間でプラスになれば僕の中では入れてもいいんじゃないかと考えています。あとは一つの機械が100万円以下で導入できるかどうかというのを考えますね。CTのような大型機は別ですよ。
ただそういったツールが100万円以下で導入できるのであれば、もしうまくいかなかった場合、痛いですけど、でも勉強代、授業料だと思えるんです。あとは今いろんな補助金がありますよね。この補助金や助成金が使えるのかどうか、というのを加味して決めています。あとは今の売り上げからどう費用を捻出するかとかっていうのを考えているくらいでしょうか。

あと、こういった場合の成果を売り上げからじゃなくて、時間対効果で見るようにしてます。例えば、スキャン。今までであれば型どりに10分の時間がかかっていたとして。それがスキャンでやると、2分で終わるとなると、その余った8分でできることがありますよね。それは他の売り上げに繋がっていくわけです。受付もアシスタントも、衛生士も例えばあるものを使うことによって時間がすごく短縮になるってなったら、他の業務ができる、そうなるとどんどん時間対効果が上がっていくんですよね。
会計や予約にかかっていた時間もそうです。1人10分かかっていたことを5分で終わるってなると、2人分見られる。効率が2倍ですよね。単純に売り上げは倍になります。それを先に言ったように5年たてばどのぐらいの差になっているのかなと考えると相当なものになると思うんです。
さらに言えば、スタッフの休み時間も確保しやすくなるわけです。
-確かにそうですね。
佐久間:もう一点、業務効率化ツールを導入することのポイントを挙げるとすれば、他の医院さんでやってなかったり、使っていないようなシステムや機械を導入すると、患者さんの方で「あそこは何かすごいことやってるよ」というような評判が立ったりすることがあるんです。
例えばPay Light(歯科医院向けクレジットカード決済端末)であれば、「カードで支払えて簡単だな」とか「待たないですぐ会計してくれるんだ」というふうに結構、患者さんはポジティブに感じてくれているんですよね。
それに僕らも合わせて、時間通りに始めて時間通りに終わらせる。なんなら少し早く終わらせたりしていると、患者さんからの信頼も上がっていくし、遅刻する患者さんも減ってくるんですよ。
逆に待ち時間が毎回のように発生しているような状態だと、患者さんの方も「あそこ行ってもどうせ待つし」ってなってくる。そうするとどんどんどんどん遅れてくる。遅刻してくる人も増えてきて医院としては多くの患者さんを捌けなくなるわけですから損失になっていくんですよね。
患者さんの時間、僕たちの時間、みんなの時間をトータルでお金に換算すると、業務効率化のツールを導入することによって相当のプラスになってると僕は思いますね。
-本当に直接的な成果と間接的な効果があるわけですね。
佐久間:そうですね。宣伝になって、広告になって、あそこは最新の物があるからねとなっていくわけです。
仮に駄目だったとしても100万円というラインを作って導入していれば次に活かせるかなっていう感覚が僕の中にはあるんですよ。でもこれが1000万だったら致命傷になってしまいますけどね。
-いろいろ取り入れた中で、佐久間先生の中で一番取り入れてよかったなというツールはどんなものですか。
佐久間:コロナのときに、補助金を使って自動精算機を入れたんですよ。これは良かったと思いましたね。厳密にいうと導入をしたのはコロナ前だったんですが受付の人たちが疲弊していて大変だってなっていたので入れたんです。
-その後にコロナが来たと。
佐久間:はい。それで補助金で機器を導入したりすると担当した人たちがちゃんと正しくお金は使われているかチェックに来るんですよ。その時担当の人に「先生は先見の明がありますね。今、みんな自動精算機を入れたいと思ってますけど、供給が追いつかなくて導入できないんですよ」と言われたんです。
-なるほど、積極的にそういうものを取り入れていたからこその結果ですよね。
佐久間:そうかもしれないですね。あと効率化ってツールを入れるだけじゃないんですよ。この辺りの地区では院内を土足にしたのもうちが最初なんです。雪国なので、患者からもスタッフからも最初は結構反発を受けたりもしたんですけど、絶対やるって決めて、そこは少し無理やりやりましたね(笑)でも今やスタンダードと言えることだと思いますし、時間効率を考えたら大事なことだと思ったんです。

-いろいろとお話を伺いましたけども、受付の対応の中で電話対応が占める割合はどれくらいあると感じていますか?
佐久間:多分3割ぐらいはあるのかなと思いますね。
-それは少なからずの負担にはなりますよね。
佐久間:そうなんですよ。だから本当は、もし僕にいっぱいお金があって、何も問題がないのであれば自前のコールセンターを作りたいんですよ。コールセンターを作って医院の電話がいっさい鳴らないようにしたいんです。そうはいっても簡単にできることではないし、そんなたくさんのお金もないんで無理なんですから、こういったスマートチェックアウトさんが提供している、ペイたんコールのような電話自動応対サービスを使う。もしくは、遠隔で、僕や僕のスタッフが自宅で、またはどこからでもできるような電話応対システムがあればなとは思ってます。
後編に続く
佐久間 利喜(さくま としき)
歯科医師・歯学博士
1998年岩手医科大学大学歯学部卒業。特定の科目に拘らず、広く臨床を学びたいという思いから1998年〜01年(医)大樹会 小笠原歯科クリニックに勤務。2001年には新栄町歯科医院を開設する。2011年には新潟大学大学院(口腔生理学講座)に進み博士号を取得。後進の育成を含めた歯科医療に従事、貢献している。
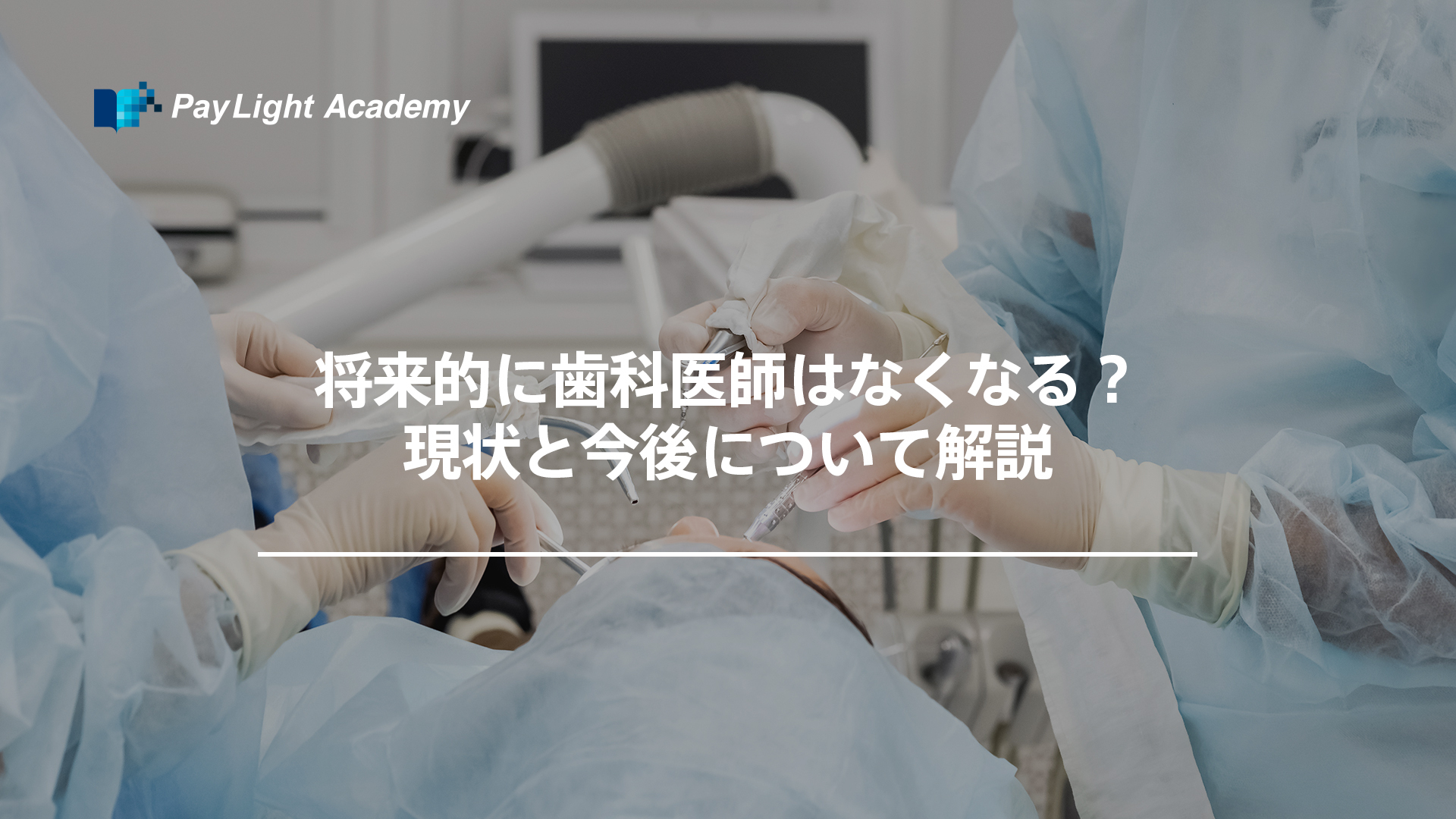
2024.04.02
経営
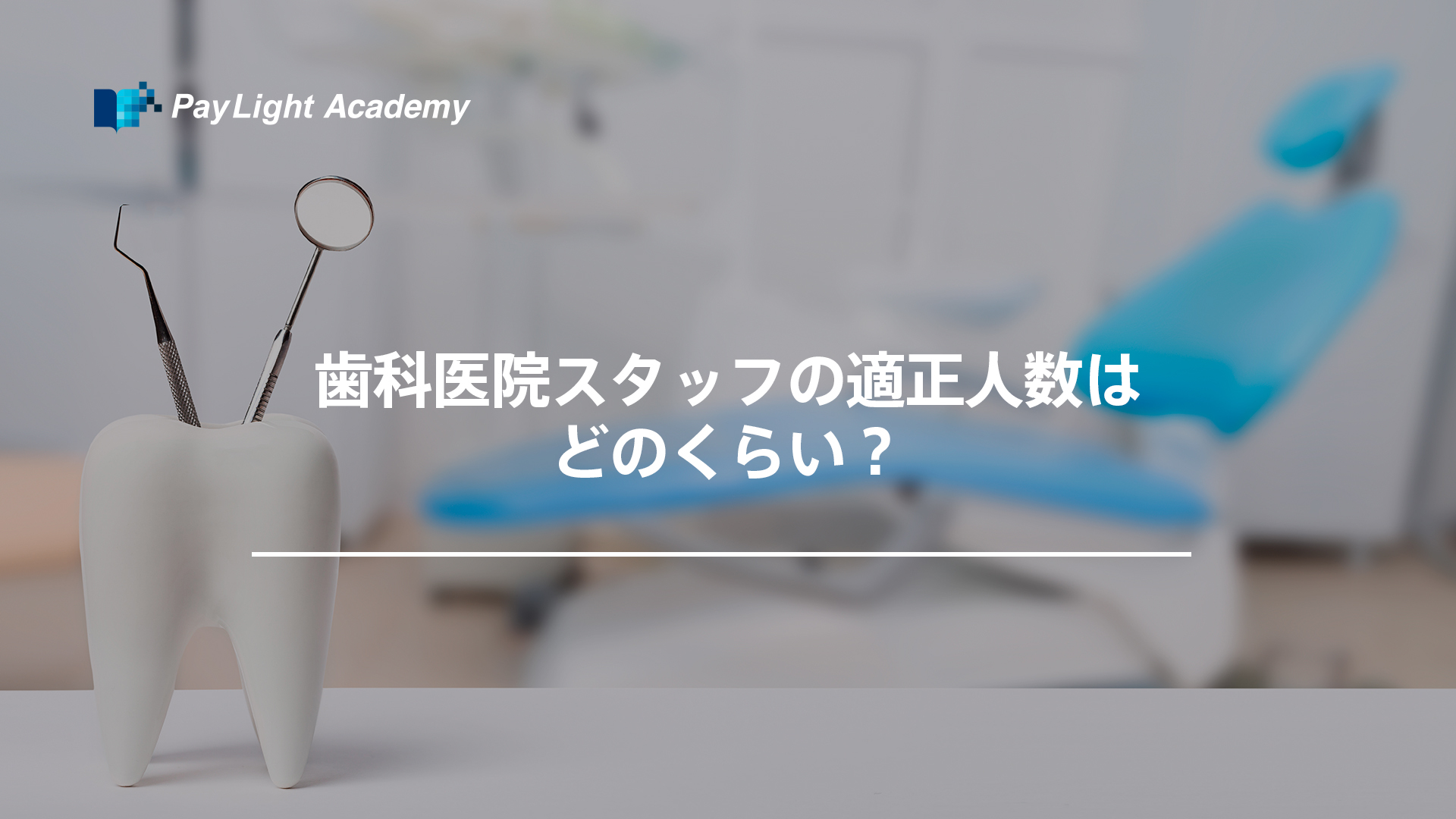
2024.03.11
経営
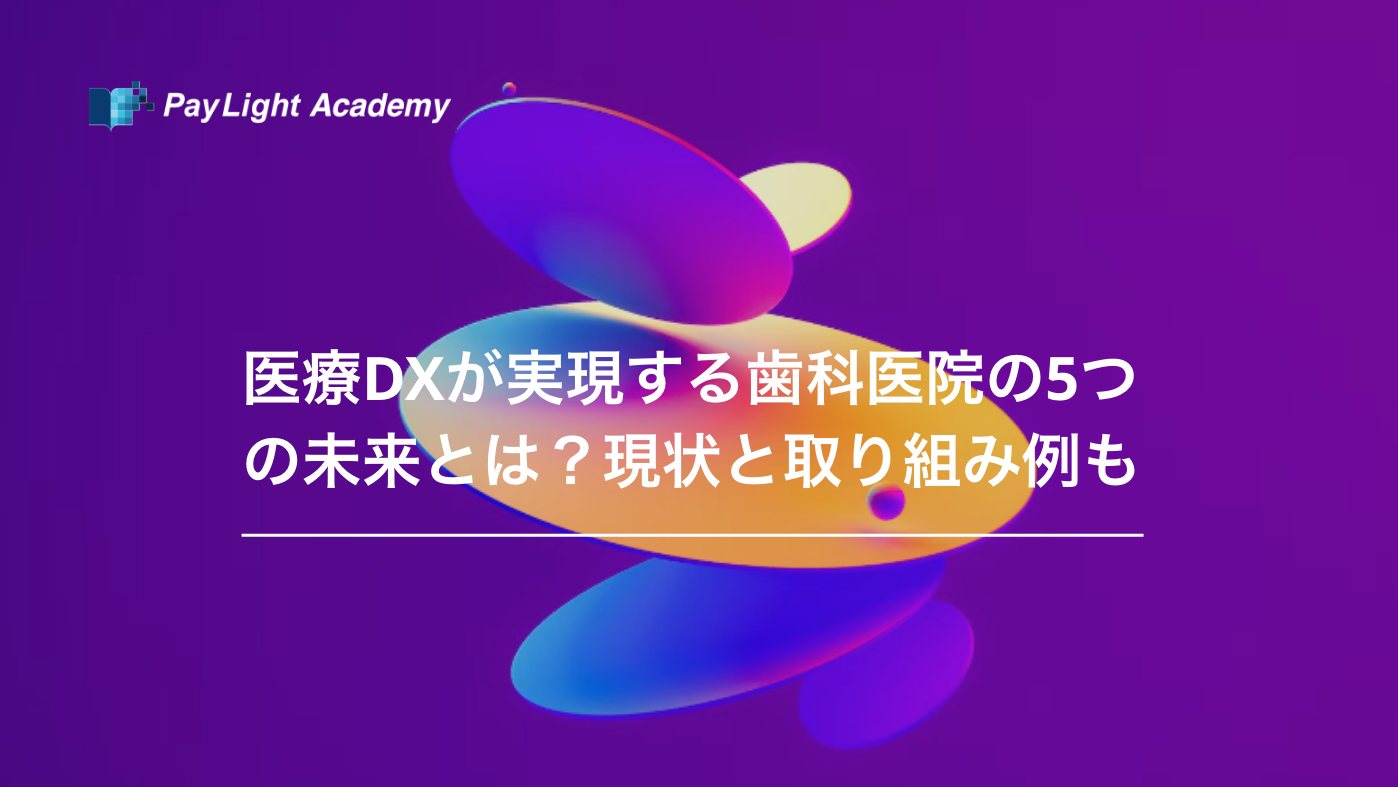
2023.12.13
テクノロジー

2023.12.13
経営
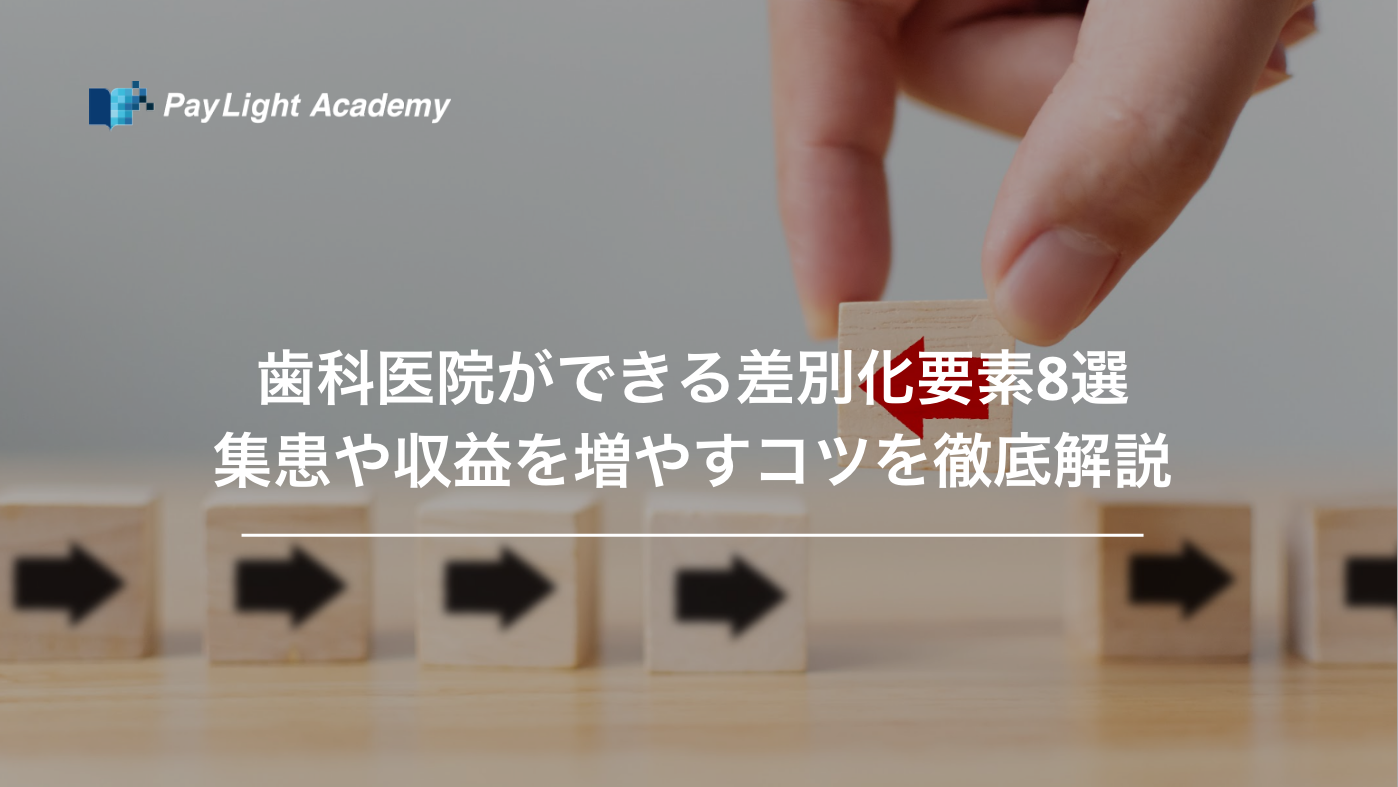
2023.12.13
経営
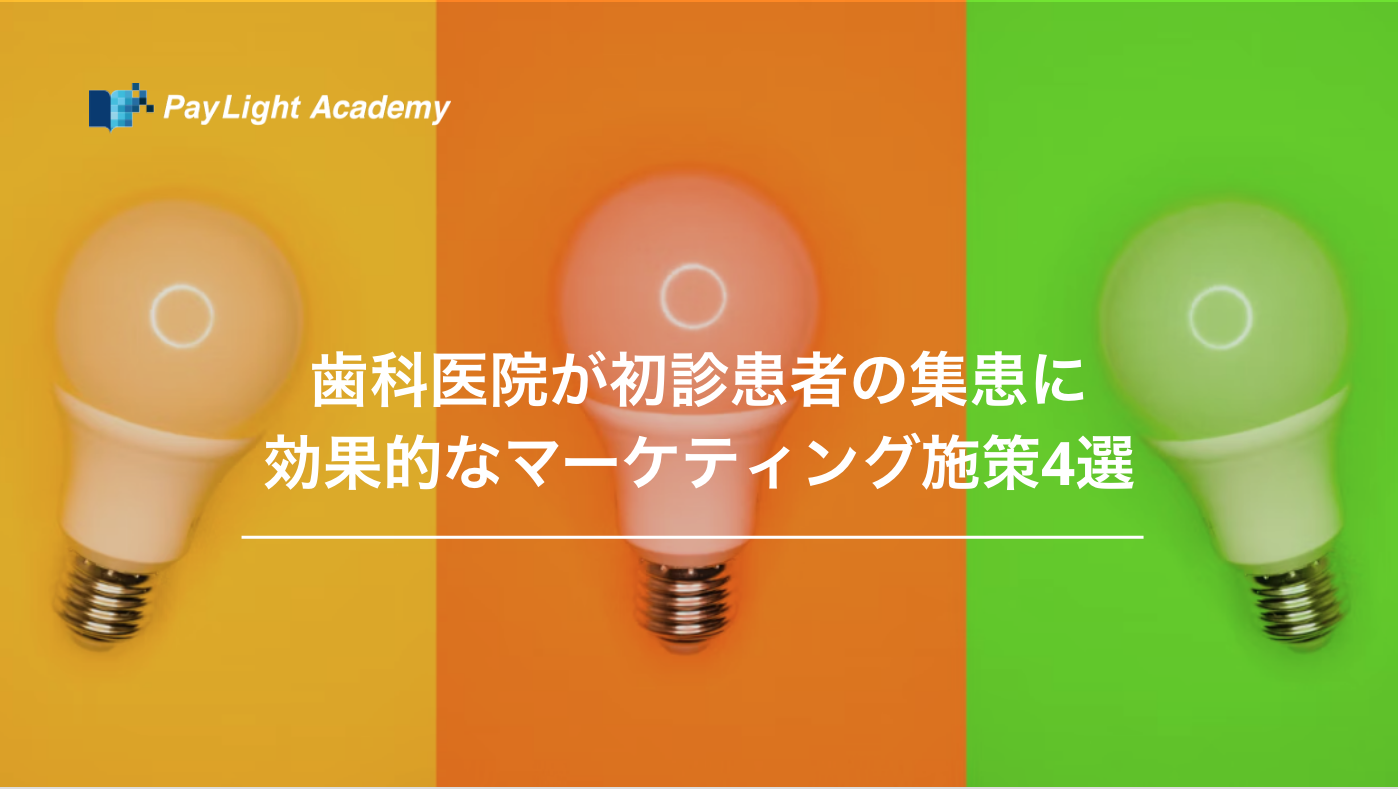
2023.12.13
経営
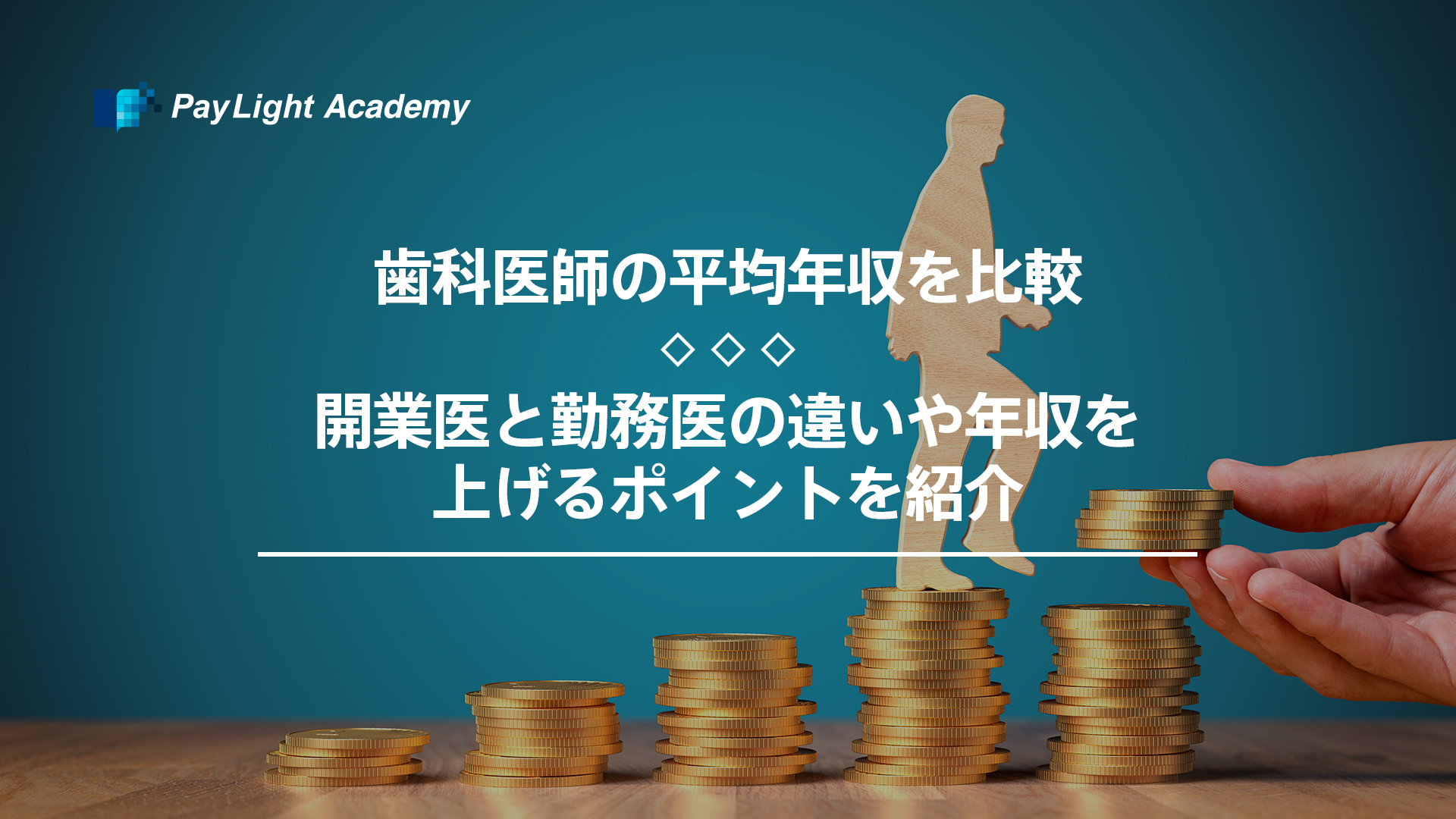
2024.03.15
経営

2024.05.10
テクノロジー